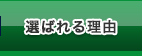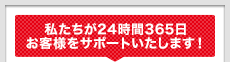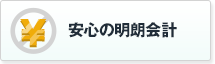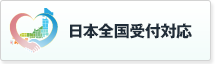庭に広がる緑の一面。芝生は外観がよいですし、緑は落ち着ける色なので、安らぎのひとときを味わっているでしょう。でもそんな芝生をよく見ると、なんか茶色い物体が…。これが落ち葉などだったらよいのですが、よく見るとキノコではありませんか!
芝生にキノコが生えるのはイメージにないかもしれませんが、実際芝生の生える場所はキノコにとっても繁殖しやすい場所なのです。今回はそんな芝生とキノコの関係性について、ご紹介していきます。
「どのようなキノコが、なぜ芝生に生えてくるのか」といった疑問から、繁殖してしまったキノコへの対策まで。このコラムを読めばキノコマスターに一歩近づきます。芝生のキノコにもオサラバできますよ。ぜひ参考にして、緑広がる芝生を取り戻していきましょう。
目次
芝生から生えるキノコ、主な種類を教えて!
芝生にキノコはほぼ必然、といえてしまうくらいに芝生にキノコは生えやすいです。そして生えてくるキノコは1種類ということではなく、いろいろな種類が生えてきます。まずは芝生に生える、代表的なキノコの特徴から説明させていただきます。
【シバフタケ】
「シバフタケ」、芝生に生えるために誕生したような名前のキノコですね。そんなシバフタケの大きさは小さめ、茶色いキノコで成長すると傘を開きます。ナメコの仲間のキノコで、夏から秋にかけて発生します。
発生するときは固まって生えるのですが、ときどき円状になるように生えてくるのも特徴です。日本ではあまり食用にはされていませんが、ヨーロッパではシバフタケを食用としている場所もあります。
【ハラタケ】
ハラタケは春から秋にかけて発生するキノコです。傘の色が白く、マッシュルームに近い存在のキノコ。傘の裏の色は最初ピンク色で、徐々に茶色になっていきます。ハラタケを食用としている国もあります。
ハラタケも群れて繁殖し、ときどき円状に生えてきます。種類によっては毒を持つキノコもあるのですが、日本ではまず生えていないので安心してください。
【キコガサタケ】
初夏から秋にかけて発生するキノコです。淡いクリーム色で細長い茎に三角の傘が乗っているような形が特徴です。食用になることはなく、単体や数本程度で生えてきます。
【ヒメホコリタケ】
シバフタケとともに、芝生に生えやすいキノコです。白く球のような形が特徴で、表面にトゲがあります。梅雨から秋にかけて増え、群れて発生したり、円状に生えたりする場合もあります。
表面のトゲがないヒメホコリタケを「チビホコリタケ」といいます。ヒメホコリタケが成長をすると、穴が開きそこから胞子を出して繁殖していきます。
なぜ芝生からキノコが?生える原因はなんですか?

いろいろな種類のキノコが芝生から生えてくるのですが、なぜ芝生からキノコが生えてくるのでしょうか。芝生の生えているところに雨が降り続いた場合、土のなかに湿った状態が続きます。
湿った土のなかではキノコの菌が成長しやすい環境になり、キノコが生まれ、成長していくのです。芝生の芝を維持、成長させるために水は必要不可欠です。そんな水が原因でキノコも発生するので、芝生とキノコは切り離せない関係といえるかもしれません。
キノコは取り去るべき?放置による影響とは
芝生にキノコが生えたところで、毒キノコではないので人体に影響はありません。ではなぜキノコの除去が必要になってくるのでしょうか。ここからは芝生にキノコが生えることの影響について、説明していきます。
●キノコが水分を奪っていく
キノコは芝生から生えている部分だけでなく、根っこのように土のなかでも成長をしています。「菌糸体」と呼ばれる糸状のもので、成長が早いのが特徴です。
キノコが増殖すると土のなかの菌糸体も増殖され、層のようになっていきます。その層が広がると、土のなかの空気や水分を奪っていき、芝生に影響を与えてしまいます。
芝生は土のなかの栄養素が減っているので、芝生の色が濃くなったり、変色して枯れていったりしてしまいます。最悪の場合は枯れてしまい、芝生の交換となってしまいます。
●胞子を撒き散らして増殖してしまう
キノコの増殖の仕方は胞子を撒き散らすことです。胞子が風に乗り、土のなかに入り栄養素を吸収し、成長していきます。とくに芝生上ではキノコが固まって増殖しやすいといわれています。芝生にキノコの山があると、きれいな緑の外観が損なわれてしまいますよね。
また先ほど紹介したとおり、キノコは土のなかの養分や水分を奪っていきます。芝生に悪影響が出るので、最悪の場合枯れてしまうことにもなりかねません。放置することにより増殖してしまうため、可能な限り早めに対策をおこなうようにしましょう。
期待大!キノコ対策は薬剤と芝生手入れがおすすめ

キノコが繁殖してしまうと、芝生にも影響を与えてしまいます。きれいな緑の芝生を保つためには、キノコの駆除が必要となるでしょう。ここからはそんな、キノコの対策方法についてご紹介していきます。
【薬剤散布でキノコもショボーンとさせちゃいます】
キノコが大量に繁殖し、キノコ駆除や芝の管理が難しくなってしまった場合は、農薬を散布する方法があります。またキノコが円状に繁殖している状態。いわゆる「フェアリーリング病」になった場合も薬剤散布しましょう。
キノコ対策で使用する農薬は「グラステン水和剤」という薬品です。しかもグラステン水和剤を散布すると、効果が出るのはキノコの駆除だけではありません、再発予防や芝生の治療効果も期待できるのです。
芝生に生えたキノコを駆除できるうえ、芝生の根の成長を促進してくれます。グラステン水和剤を散布するときの注意点としては、吸い込んだり、飲み込んだりしないようにしましょう。とくに、小さなお子さまがいるようなご家庭は要注意です。
【芝を手入れしてキノコ菌もアタフタ!】
芝生に発生するキノコを予防するためには、芝の手入れも有効です。芝の手入れをすることは、キノコの発生源となる土のなかの対策もできますし、菌糸体の増殖を防ぐことにもなるのです。そんな芝の手入れには、下記のような種類があります。
●土のなかの通気性をよくする
芝生を元気にするためにおこなう作業「エアレーション」。ローンチスパイクやガーデンスパイクなどの特殊な道具を用いて、地面に穴をあける手入れの方法です。エアレーションをおこなうことで、土のなかに空気が入り、通気性がよくなります。
土のなかの通気性がよくなると、キノコ以外の菌類が増殖しやすくなります。キノコが増殖するためには、キノコ菌が固まった環境が必要。エアレーションをすることで、キノコが育ちやすい環境を壊すことができ、同時に増殖を抑えることができるのです。
●サッチングをする
サッチングとは芝生の上にある「サッチ」を取り除くこと。サッチとは芝生で刈った草や枯れた葉が蓄積された層のことをいいます。秋の「落ち葉集め」をした状態をイメージするとわかりやすいでしょう。
キノコにとって、サッチは格好の栄養源です。放置しておくとキノコはみるみる成長します。芝生を作った以降、2年目からできやすいので、定期的にサッチングをおこないましょう。
●キノコを刈り取る
芝生の地上部分、キノコの傘から胞子が飛び出して繁殖していきます。キノコの地面から出ている部分を子実体(しじったい)といいます。この子実体を取り除けば、胞子を撒き散らす方法がなくなり、キノコ対策につながります。
●芝生地帯の風通しを良くする
キノコ菌が地中で水分を吸い取り成長します。つまりは土のなかに水分が溜まってなかったらキノコ菌は成長せず、繁殖もしにくくなります。庭などの芝生部分周辺で、風の流れをさえぎるモノがあれば、撤去して風通しをよくしましょう。
【キノコ博士であるプロにキノコの対策をしてもらおう】
キノコの繁殖がとても多く、効果のある手段でキノコ対策をしないのであれば、キノコ駆除の業者に依頼をしてみましょう。業者の人はキノコについて、詳しい知識と対応方法を知っています。増殖が進んだキノコ駆除も、適切におこなってくれるでしょう。
また、キノコを取り除いたあとには再発防止の対策やアドバイスをもらうこともできます。早くしっかりとしたキノコ対策をするのであれば、費用も大掛かりな対策に比べてかかりません。気になるようであれば、早めの依頼が鉄則といえます。
まとめ
芝生がある限りキノコは生えてきます。とても高い確率で生えてきますので、芝生にはキノコが生えてくる前提で考えたほうがよいでしょう。芝生に生えてくるキノコは基本的に人間には無害。しかし繁殖しすぎると、最悪芝生を枯らしてしまうので、対策が必要です。
芝生でのキノコ対策はいろいろな方法があります。自分の状況にあった対策をとっていってください。また自力ではお手上げのときは、キノコ駆除の業者に頼んでみるのもよいでしょう。